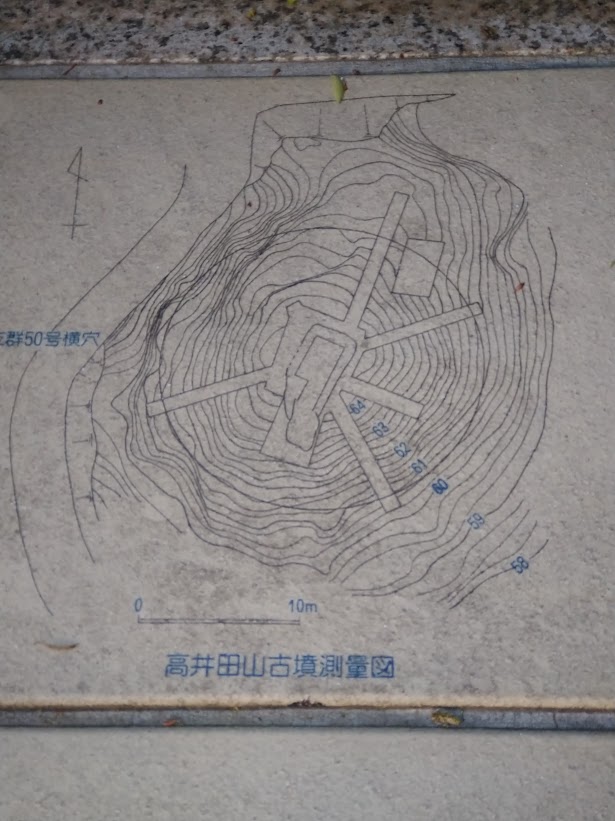畝傍山。神武天皇陵と橿原神宮を山麓にいだき、この国の始源のすがたを可視化した聖なるお山は、荘厳神聖な山容で大和盆地に屹立している。
しかし、いまわたしたちが眺める畝傍山の樹相は、明治期以降に、往古の神々しさを取り戻す、などとした声の末に、ヒノキ、カシなどを植林したものだ。
古い時代のお山の写真を目にしたひとは、現在とは幾分違った、そのおだやかで、あまりにも優しい印象に驚くだろう。
そして、昔のそんな時代の畝傍のお山に接したいと願うのならば、今も山中におられる眼福地蔵に会いに行かれるといい。
地蔵様はきっと、来る人すべてを優しく受け入れてくださる…。
~目次~
眼福地蔵への道案内

畝傍山の登山道といえば、橿原神宮の北参道を進んだ先にある道、あるいは畝火山口神社の脇からはじまる道が、よく整備されていて比較的知られているが、他にも、いくつかの登山道がある。
お山の西麓にある、第四代 懿徳天皇陵 (いとくてんのうりょう) に沿うようにのびる道もそのうちのひとつだ。
陵を右手に眺め、やがて耕作地のあいだをぬけて行くと、いよいよ山中に踏み入ることになる。
そして、急な上り坂を進むうちに、ほどなくすると眼福地蔵のお姿を拝むことができるだろう。
眼福地蔵にまつわるお話

やまとの国で
昔々、やまとの国中が戦乱 (いくさ) にあけくれておった頃、村人たちは、どうかまた穏やかな日々が戻ってきますようにと、毎日のように畝傍のお山におられる地蔵様に手を合わせに来ておった。
そのなかには、盲 (めしい) の幼娘 (おさなご) の手をひいた母娘の姿もあった。
そして戦乱がおさまると、地蔵様のもとをたずねるひとのすがたもすくなくなり、いつしか地蔵様は落ち葉に埋もれてしまわれたそうな。
それから、幾年月がながれた。
幼き日々のおもいで
ひとりのおばあさまが、かたく目を閉じて畝傍のお山にむかって手を合わせておられた。
ゆっくりと目をあけてもまだ、両手を合わせたまま、じっとお山を見上げておられた。
通りかかった村人が、不思議とばかりに話しかけた。
「どうかされましたんか」
おばあさまは村人のほうを向いてほほえまれた。
「へえ、ここにちがいないと思いましてな。なつかしいわ」
それから、もう一度お山のほうへ向き直って語りはじめた。
まだ、わてが童 (わらべ) やったころな、ととさんは戦乱にとられてしもうた。そんでな、かかさんに手を引かれてな、いっつもここの畝傍のお地蔵さんに手を合わしに来てましたんや。わては目が見えやせんかったんでな。
ととさんが帰って来はりますように、ととさんが帰って来はりますように…。
「なあ、お地蔵さんどんなお顔してはんのん」
「きれいなお顔やで。きれいなお目、きれいなお鼻、きれいなお口や」
けどな、よう悪さもしましたわ。
お地蔵さんのまわりの山道を走ったりしてな、ようかかさんに怒られましたわ。見えんでもな、なんべんも来てたらな、道、わかるようになりますねん。
「あんた、なにやってんねん。すべって落ちますやろ」
そんなときはな、かかさん決まってこないにゆうてはりましたわ。
「あんた、紅色のええのん着てますんやで。おとなしいしとき」
紅色ってなんやてきいたらな、暮れのお日さんの色や、いちばんきれいな色やて、そないにゆうてはったな。
貧しかったにきまってますがな。そんなええのん着てたはずありませんわな。せやけどな、わてを嬉しがらそうとして、そないゆうてはった。
そうこうするうちにな、かかさん死んでしもうてな、わては縁者のひとに引き取られた。それからはな、クニからクニ、旅から旅や。そら辛 (つろ) おましたで。
けどな、いっつもかかさんがゆうてはったことを思い出してましてん。もう一度 (いっぺん) ととさんに会えますで。ととさん帰って来はりますで、てな。
わてはととさんの顔なんぞ、覚えてまへんのやで。それでもな、ととさんに会 (お) うたら分かるて、ずっと思うてましたんや。
せやせや、わての目な、いつのころからか見えるようになってましてん。治ってましたんや。
ととさん、ととさん…。
せやけどな、わてもこんな歳になってしもうた。もう、ととさんも生きてはいはりませんやろ。
ととさんと、かかさんと、三人で畝傍のお山のそばにおったころ、あのころが一番しあわせでしたんやろな。
眼福地蔵
神妙な面持ちではなしを聞いていた村人は、持っていた杖をおばあさまに差し出した。
「これを持って行きはったらよろしいで。地蔵さんまでは、まだだいぶとある。しかも急坂や。ここのお山の松の木で作りましたんや。ちょっとごつごつしてますけどな」
「おおきに」
おばあさまは畝傍のお山に入っていかれた。
山道を登ってしばらくすると、ドタドタとなにやら駆けおりてくる音。
おさなごが、走ってきた。
「あんた、なにやってんねん。すべって落ちますやろ」
はっとして、おばあさまは駆けあがられた。
おさなごは、どこへかいってしまった。
足音だけが、まだ響いていた。
おばあさまが、ふと反対のほうを見ると、もうそこにお地蔵さまがおられた。
ゆっくりと近づいてみる。
「ああ…、ああ…」
おばあさまはくずれ落ちて、お地蔵様にとりすがった。
両の目から、たちまち涙があふれでた。
「なんでや、なんでや…」
お地蔵様のお顔を覆っていたおばあさまの掌 (てのひら) が、ぶるぶる震えてゆっくりとずり落ちた。
「このお地蔵さん、お目があらしまへん。お目があらしまへんで」

おばあさまの嗚咽のあまりの大きさに驚いたものか、お山のむこうの池ではねを休めていた水鳥たちが、いっせいに飛び立った。
そのなかには、まるで身を寄せ合うように飛ぶ、三羽の鳥がいた。
あれはきっと、ととさま鳥、かかさま鳥、幼娘鳥の三羽の親子鳥にちがいない。
親子鳥は、ずっと西のほうにある二上のお山、あの二つの峰のあいだに暮れ落ちる夕日にむかって飛んでいった。
そんなことがあってから、村人たちはこの畝傍の地蔵様のことを、いつしか眼福地蔵と呼ぶようになったそうな。
傘さす地蔵様

わたしは眼福地蔵に会いにいってきた。
たずねるひとが絶えないのだろう。
まわりは掃き清められた様子で、花と水が供えられていた。
静かに手を合わせた。
畝傍山の山中に、傘をさした仏様がおられたよ。第4代 懿徳天皇陵のわきの細い登山道から登っていったところにおられたよ。#畝傍山 #橿原市
— 松野文彦 (@ma2no_z32) 2024年4月12日
#石仏 pic.twitter.com/t5sCUeRoKv
お地蔵様は、傘をさしておられた。
雨にふられては困るだろう、日照りが続けば暑かろうと、そっと傘をさしかけたひとがいるのだ。
誰なのだろう。
きれいな朱色に身をつつんだおさなごではあるまいが。
後記。
眼福地蔵のお話は奈良県にあってもほとんど知られてはおらず、わたしも、ごく最近になって知ったものだ。現代に伝えられている眼福地蔵のお話は、拙文よりももっと簡潔で短い。幼娘は朱色の着物をきてはおらず、老婆が畝傍の山中で幼いころの自分と出会うこともない。親子鳥は二上山に沈む夕日に向かって飛んではいかない。改変とのそしりは甘んじてうける覚悟を持ちつつ、わたしは民話、伝承といったものは時代とともに変わっていくことを是とする立場にいる。
現代において読まれているグリム童話は、周知のように、グリム兄弟が記したものとは、おおくの点で違っている。それは日本の昔話においても同様だが、いま読まれている物語が偽物というわけでは決してない。
わたしはこれを書きあげるとき、原意を損なわないことに慎重に留意しつつ、より現在の読み手に眼福地蔵の慈愛が伝わるようにと願った。
読者諸賢の理解を得たい。
参考資料
橿原市 まなごの里 懿徳天皇陵 大和三山 まなご谷 畝傍山 犬養孝 畝火山口神社 真砂山 眼福地蔵の由来